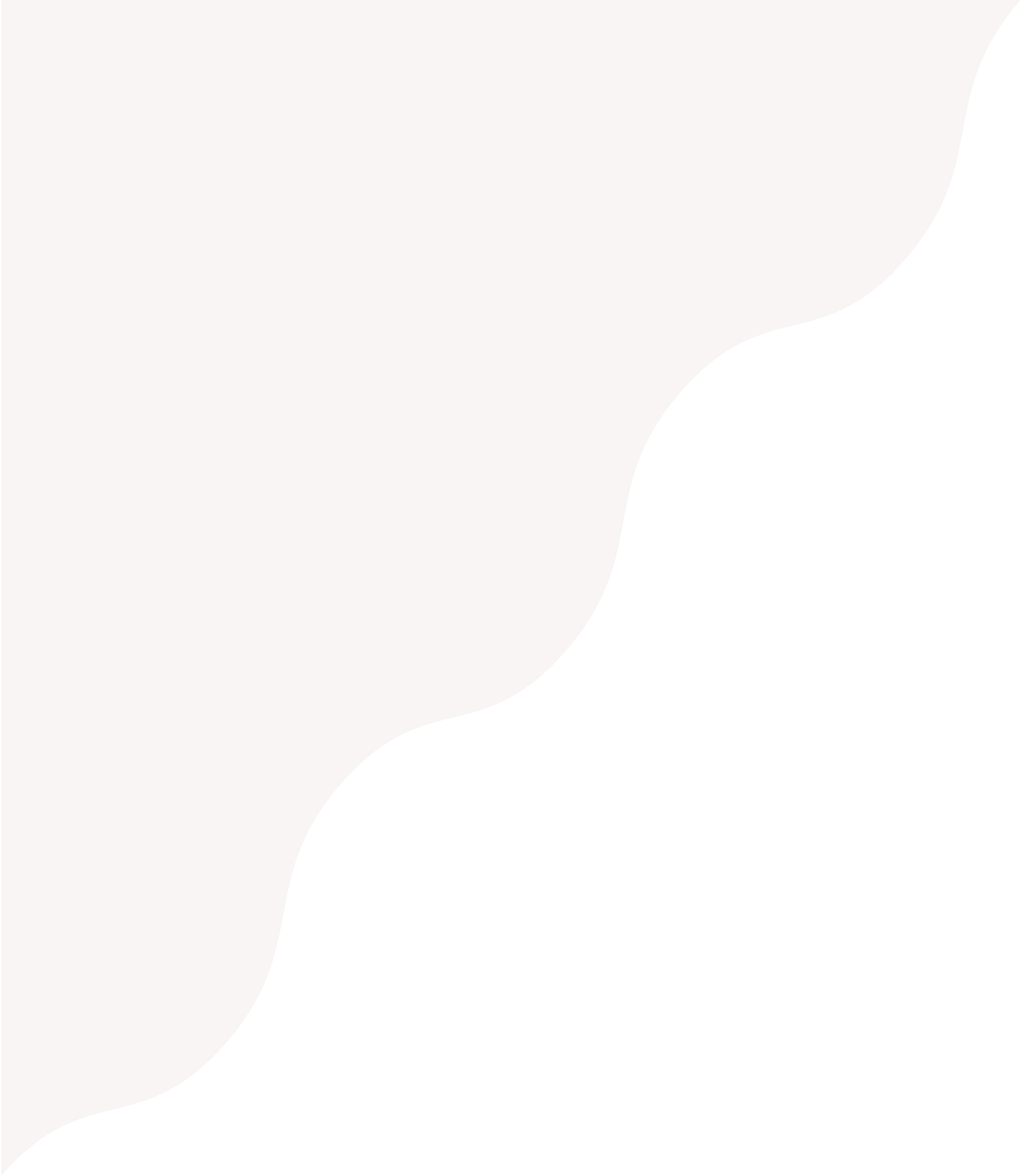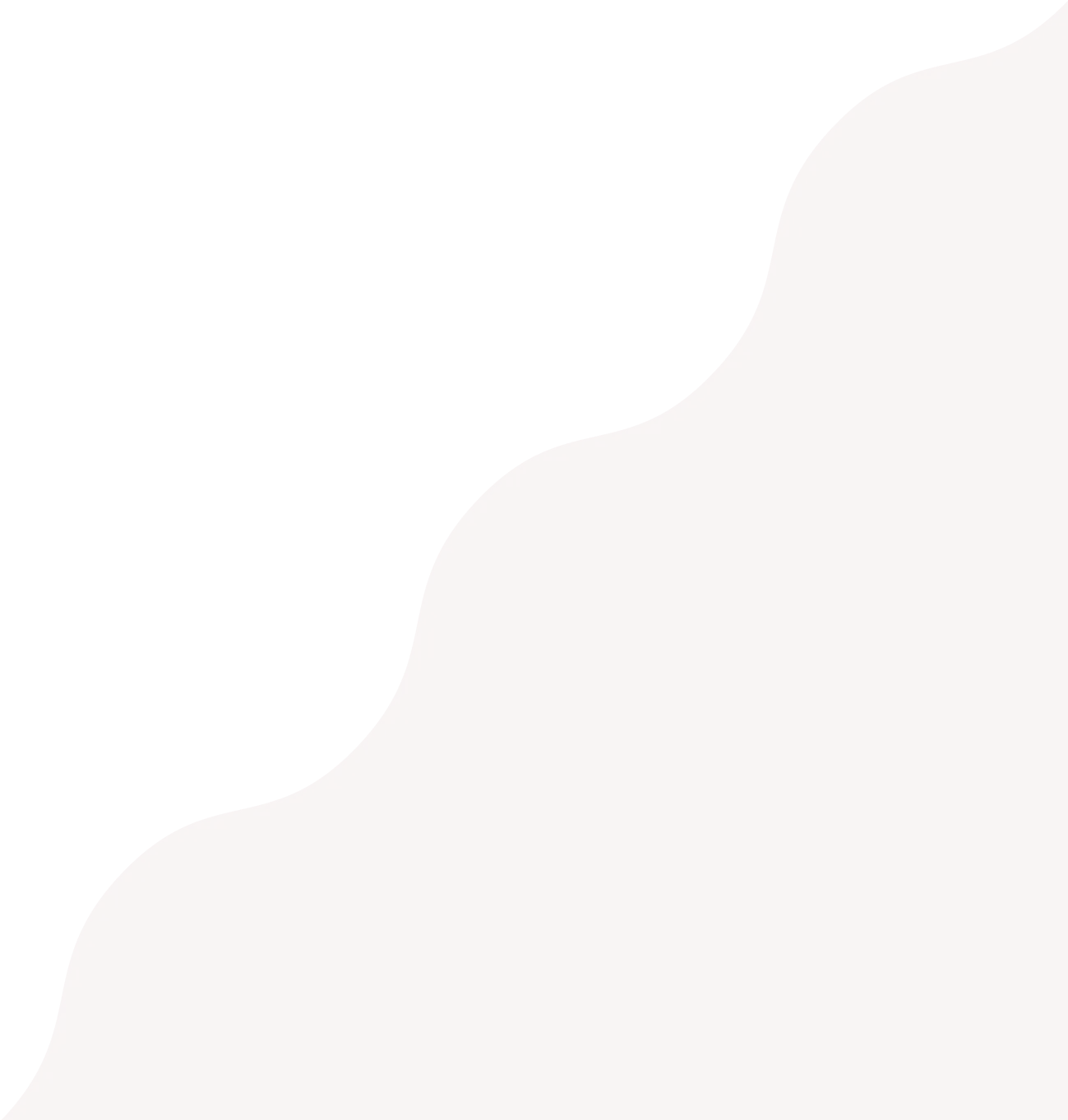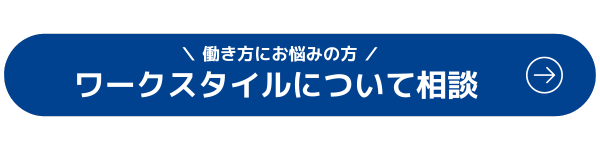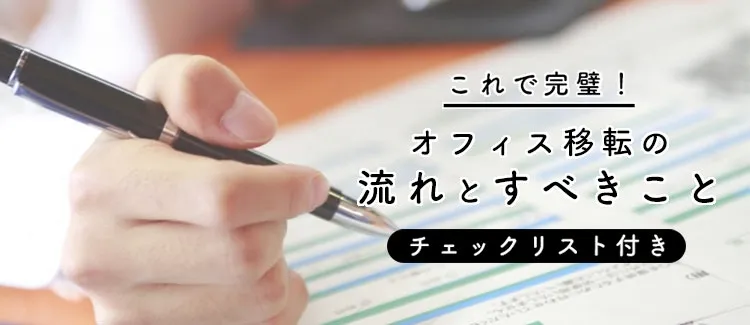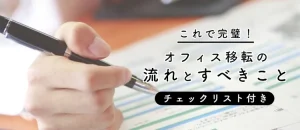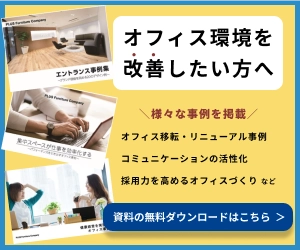社員の仕事に対するモチベーションを高めるには、帰属意識が重要であると考えられています。帰属意識が高まると、生産性の向上や離職率の低下につながる可能性があります。しかし、ハイブリッドワーク下では社員が直接、顔を合わせる機会が少なくなるケースもあり、帰属意識の低下が懸念されています。
調査によると、日本企業の社員は帰属意識が低い傾向があります。特に、ハイブリッドワーク下で帰属意識を高めるにはどのような方法があるのでしょうか。今回は、帰属意識とは何か、帰属意識が高まりにくい原因や帰属意識を高めるためのポイント、ハイブリッドワーク下における帰属意識向上の方法などについて解説します。
ハイブリッドワークについては、『ハイブリッドワークとは?テレワークの定着を実現させるポイントと注意点』の記事をご覧ください。
帰属意識とは
帰属意識とは、社会、地域、会社などの集団において、自分は組織の一員であるという意識、組織の仲間であるという意識のことをいいます。企業においては、会社の業績向上に貢献しようとする社員の忠誠心を指すこともあります。帰属意識が高いほど、組織の問題や課題を自分のこととして捉えるようになるでしょう。そして、社員間で一体感が生まれやすく、お互いに協力して目標を達成しようとする気持ちも高まります。さらに、仕事に対するモチベーションがアップし、生産性の向上につながることも期待できます。
近年は、働き方の多様化に伴い、リモートワークやフレックスタイム制を導入する企業が増えました。また、転職する人が増え、終身雇用の継続が難しいともいわれています。そのような状況のなか、企業が安定して人材を確保するためには社員の帰属意識を向上させることが重要です。社員が企業に愛着を持てば長期にわたって働いてもらえる可能性があり、離職率の低下にもつながるでしょう。多くの業界、業種では優秀な人材の確保が課題となっています。現在雇用している優秀な人材を手放さないためにも、帰属意識を高めるための施策を検討することが大切です。
帰属意識とロイヤリティとの違い
帰属意識とロイヤリティは似たようなシーンで使われる言葉ですが、帰属意識は従業員が自発的に組織の一員であることを認識する状態を指し、主従関係を前提としません。
一方でロイヤリティは、英語で忠実という意味の「loyalty」を語源にしているマーケティング用語で、企業に対する忠誠心や献身を示すものであり、企業に対して従業員が従うという主従関係が含まれています。
帰属意識が高くても、ロイヤリティが必ずしも高いとは限らないのがポイントです。
帰属意識とエンゲージメントとの違い
帰属意識とエンゲージメントは、どちらも従業員と企業の関係性を示す言葉です。しかし、両者の方向性は異なります。帰属意識は従業員から企業への一方向の感情であり「組織の一員である」という意識を指します。
一方で、エンゲージメントは企業と従業員の間に双方向の深い関係性があることを意味し、企業と従業員がお互いに貢献したいという意欲が存在します。
エンゲージメントが高い組織では高い成果が見込めますが、帰属意識だけでは必ずしも同じ結果を生むとは限りません。
帰属意識が「気持ち悪い」といわれてしまう理由
帰属意識は従来、企業と従業員を結びつける重要な概念として認識されていました。
しかし現代では働き方の多様化が進み「帰属意識」という言葉にネガティブな印象を抱く人も増えています。
その理由は、帰属意識が「愛社精神」や「社内の集団行動主義」と結び付けられがちであることが挙げられます。
また一部の企業では、飲み会や懇親会を通じて帰属意識を高めようとする文化が残っていますが、個人のワークライフバランスを重視する現代の価値観に合わなくなってきています。
そのため帰属意識を高める方法として、企業が個々の価値観や働き方を尊重する取り組みが求められています。
そもそも日本は帰属意識が低い傾向にある
日本人の企業に対する帰属意識は強いと考えられていました。しかし、アメリカの調査会社ギャラップ社が2021年に行った調査をもとに経済産業省が作成した資料によると、日本の企業で働いている従業員の企業に対する士気・熱意(従業員エンゲージメント)は他国と比べても低いことがわかります。
同調査によると、従業員エンゲージメントの世界平均は20%でした。最も高い国はアメリカとカナダで34%、最も低い国が日本で5%となっています。また、東アジアに絞ってみても、モンゴルが35%、中国17%、韓国12%、台湾8%、香港7%、日本5%で、日本は最下位です。
従業員エンゲージメントとは、個人と組織が互いに貢献し合える関係を意味する言葉です。帰属意識が強いほど従業員エンゲージメントも高まるとは限りませんが、企業にとっては重要な指標のひとつといえます。そもそも企業が従業員の帰属意識を重要視する理由は、帰属意識を高めることで自社の業績向上に貢献してほしいからです。そのため、従業員エンゲージメントは帰属意識が高まることで期待される結果ともいえます。
さらに、パーソル総合研究所が行った「APAC就業実態・成長意識調査(2019年)」をもとに経済産業省が作成した資料によると、現在の勤務先で働き続けたい人の割合も日本が最下位でした。最も高い国はインドで86%、次いでベトナム、中国、フィリピンの順で、日本は52%となっています。この調査では対象地域がインド太平洋地域に限られているものの、日本人の帰属意識は決して高くはないことを示しています。これらの調査から、日本企業の従業員は自分が所属している会社に対して不満を持っている人も少なくないと考えられるのです。
帰属意識が低いことのデメリット
社員の帰属意識が低下すると、企業の業績や自分の業務に対する関心が薄くなる可能性があります。業務の目的や意味を深く考えないまま、与えられた仕事をこなすだけになってしまうでしょう。「組織の一員」として仕事をするなかで、自分の業務や役割を自分のこととして捉えられなくなる人もいます。組織内における自分の役割が見いだせず、離職につながるおそれもあるのです。会社に貢献することよりも自分のキャリアやスキル、給与を重視するため、他社の条件が良ければ、他社へ移ってしまう可能性が高くなります。
帰属意識が低くなる理由
前述のとおり、日本の企業で働いている従業員帰属意識はそれほど高くないことがうかがえます。帰属意識が高まりにくい理由は何なのでしょうか。ここでは、その理由について解説します。
働き方の多様化
帰属意識が高まりにくい理由のひとつは働き方の多様化です。現在は多くの企業がリモートワークやハイブリッドワークなどを導入し、従業員同士が顔を合わせる機会も少なくなりました。出社をしなくてもオンラインを活用すればリアルタイムで業務連絡を行うことはできますが、オフィスに比べるとコミュニケーションを取る時間は少なくなります。
年功序列
年功序列とは、年齢が高く、勤続年数が長いほど、昇進しやすくなったり賃金が上がったりする制度です。日本は海外の企業に比べて年功序列の傾向が強いといわれています。しかし、年功序列の企業では、自分の仕事が会社に正当に評価されてないと感じる人も少なくありません。特に、若手社員や勤続年数が短い社員は業績向上に貢献しても、昇進や昇給につながらない可能性があります。そのことにより、組織への貢献度や帰属意識が低下することもあるでしょう。
終身雇用制度の崩壊
日本の多くの企業は、従業員に入社から定年退職まで在籍してもらい、労働者へ安定した雇用を提供してきました。しかし、転職や副業など、キャリアの多様化により、終身雇用は崩壊しつつあるといわれています。自分でキャリアを築きたい人にとっては、終身雇用はあまりメリットがありません。一方、安定した環境で働きたい人にとっては、終身雇用制度の崩壊は帰属意識の低下につながる可能性があります。
コミュニケーション不足
リモートワークの導入や時差出勤、業務効率化などにより、職場内のコミュニケーション不足に課題を抱える企業も少なくありません。職場内のコミュニケーションが不足すると、帰属意識が低下しやすくなるといわれています。特に、業務以外のことを話す機会が減り、職場の仲間と気軽に会話をすることが少なくなっています。
評価・待遇への不満
従業員が評価や待遇に対して不満を抱くことで帰属意識が損なわれます。
働きに見合った適正な評価を受けていないと「必要とされていない」「努力が報われない」といった感情が生まれ、企業との関係性が希薄になります。
また給与や福利厚生など待遇への不満は、従業員の健康やライフスタイルに影響を与えるため、直接的な帰属意識の低下につながります。
透明性のある評価制度や、従業員の声を反映した待遇の整備が求められています。

帰属意識が高い場合のメリット
帰属意識の高い従業員がいることで、会社の成長やビジョンの実現につながります。
ここでは、従業員の帰属意識を高めることで得られる具体的なメリットについて説明します。
働くモチベーションの維持・向上
誰かに必要とされることは、働くモチベーションになります。
そのため自分が組織に必要とされていると感じている、帰属意識の高い従業員は仕事への意欲が高い傾向にあります。
業務効率も上がり、個々の従業員の生産性向上にもつながるでしょう。
さらにモチベーションの高さは周囲にも伝わるため、他の従業員にも良い影響がおよびます。
モチベーションの高い従業員が増えることで、企業全体が飛躍的に成長します。
定着率の向上
帰属意識の高い従業員は、その企業に長く勤めたいと考えるようになります。
とくに近年は、独立してフリーランスとして働いたり起業したりする選択肢も身近になっており、優秀な社員の定着は多くの企業にとって課題です。
定着率が上がることで離職率が低下し、人手不足や採用コストの削減が可能になります。
長く働く従業員が増えることで、企業のノウハウが蓄積され、長期的な業務の安定化が実現します。
採用・教育コストの削減
定着率が上がることで、頻繁に人材を採用したり新たに教育したりする必要が少なくなります。
また帰属意識の高い従業員は、口コミで自社の良さを第三者に伝える傾向もあるため、リファラル採用で良い人材が集まる可能性もあります。
高い手数料や広告費のかかる求人サイトや人材紹介に頼らずに済むため、採用コストの削減が実現できるでしょう。
コミュニケーションの活性化
帰属意識が高い職場では従業員同士のコミュニケーションが活発化し、お互いに協力しあう環境が生まれます。
企業が従業員の居場所となることで、職位や立場の垣根を超えたコミュニケーションが生まれやすくなり、マネジメントや情報伝達効率がアップします。
また偶発的にソリューションが生まれる可能性も高まるため、組織としての成長につながるでしょう。
こういった環境を作るためには、従業員の心理的安全の確保が大切です。
それぞれの立場を尊重できる環境を構築することで、発言しやすい雰囲気が生まれコミュニケーションが活発になります。
帰属意識が低い場合に起こること
帰属意識が低いことで、組織全体のデメリットにつながることもあります。ここでは、帰属意識が低い場合に起こることを具体的に解説します。
自分の仕事や組織の目標に対する関心が薄くなる
帰属意識が低い従業員は、自分の仕事に対する関心が薄くなりがちです。自分が行っている業務で企業にどのように貢献できるのか、あるいは顧客の役に立っているのかを考えずに仕事をしてしまいます。また、部署や会社全体が目指す目標にも関心がなく、自分の役割や業務の重要性を認識できない可能性もあるでしょう。
組織全体の生産性低下につながる
自分の業務や組織全体の目標に対する関心が薄い従業員が増えると、組織全体の生産性低下につながる可能性があります。社員が自ら向上したい、会社に貢献したいという意識が生まれにくく、仕事に対するモチベーションも下がります。モチベーションの低下は個人だけの問題ではなく、職場内全体で士気が低下する原因にもなるのです。
離職率が高まる
職場内の士気が低下すると、仕事にやりがいを感じられない人が増え、離職率が高まるおそれもあります。離職する社員が増えた場合、新しい人材を採用しようとしても、人手不足が深刻な業種では、新しい人材の確保が難しいケースも少なくありません。また、たとえ新しい人材が確保できたとしても、人材育成には時間とコストがかかります。さらに、職場環境を改善しなければ、再び離職につながる可能性もあります。
帰属意識を高めるためのポイント
社員の帰属意識が高まれば、企業にとってもプラスになります。そのため、帰属意識を高めるための施策を行うことを検討するとよいでしょう。ここでは、帰属意識を高めるためのポイントを紹介します。
企業理念や組織の目標を共有する
帰属意識を高めるには、社員と自社の企業理念や組織の目標を共有することが重要です。企業理念とは、企業が事業を行ううえで重視している価値観や考え方のことをいいます。「なぜこの事業を行っているのか」「企業としてどのように社会貢献するのか」など、会社が掲げる理念に共感できれば、社員もその理念に沿った行動をするようになるでしょう。また、会社や部署としての目標を共有すれば、組織として同じ目標に向かっているという意識を持つ可能性があります。
社員の役割を明確にする
組織内での自分の役割が明確になっていないと、自主的に業務を進めることができません。上司からの指示がなければ、どのように業務を進めればいいのか自分で判断することが難しいでしょう。そのため、組織内における社員の役割を明確にすることが重要です。役割が明確になれば自分が組織に貢献できているという意識が生まれやすくなります。さらに、組織の一員として自分の役割を担っているという気持ちになり、会社や組織に対する帰属意識も高まるでしょう。
コミュニケーションを活性化させる
帰属意識を高めるためには、社内コミュニケーションを活性化させることもポイントです。業務の進捗状況を確認したり、情報共有したりすることで、メンバー同士の一体感が生まれやすくなります。また、役職や部署を超えたコミュニケーションも重要です。普段ほとんど会話をする機会のない上司や他部署のメンバーともコミュニケーションを取ることで、組織の一員であるという意識が芽生えるでしょう。
社内コミュニケーションについては、『職場内のコミュニケーションが不足する理由は?原因と対策を考えよう』や『社内コミュニケーション活性化のために試したい、9つのアイデア』の記事もご覧ください。
ワークライフバランスを重視する
働き方改革が進むなか、ワークライフバランスを重視する人も増えてきました。ワークライフバランスとは、仕事とプライベートを両立させ、うまくバランスが取れている状態のことです。仕事だけでなく家族や友達と過ごす時間も大切だと考える人が増えているため、企業としても社員のワークライフバランスを重視することが必要になってきています。ワークライフバランスを重視することで、社員は気持ちに余裕を持って仕事に打ち込めるでしょう。社員が今の会社で働くことで充実した人生を送れていると実感できれば、会社に対する帰属意識も高まる可能性があります。
ハイブリッドワーク下で帰属意識を高める方法
近年、リモートワークとオフィスワークを組み合わせたハイブリッドワークを実施する企業も増えてきました。ハイブリッドワークは、ワークライフバランスを実現しやすいというメリットがあります。しかし、ハイブリッドワーク下では、リモートワークとオフィスワークをする社員に分かれるため、社内コミュニケーションが少なくなるというデメリットもあります。そのため、社内イベントや面談、ミーティングなどの頻度をあげたり、対面でコミュニケーションを取る機会をつくったりするなど、孤独感を軽減する工夫が必要となるかもしれません。
また、オフィスにミーティングスペースや集中ブースなどを設置し、出社してもオンラインでの打ち合わせがしやすい環境を整えたり、社員が気軽にコミュニケーションを取れるようカフェスペースやハドルルームなどを設けたりすることも効果的です。こうしたスペースとあわせてフリーアドレスを導入すると、作業スペースでも普段はあまり話さない社員同士がコミュニケーションを取りやすくなります。
帰属意識を高めるためには、自分自身の役割や居場所を意識できる機会を設けることが大切です。一人ひとりに働きかけることも重要ですが、自然と帰属意識を持てるような制度や環境をつくることもひとつの方法と言えるでしょう。
プラスでは気軽に社員同士が雑談するためのカフェスペースとして、5 TSUBO CAFEを提供しています。雑談のなかから生まれる新たなアイデアやコミュニケーションが帰属意識を高めることにつながるでしょう。
あわせて、ハイブリッドワークについてより詳しく知りたいかたは、『ハイブリッドワークとは?テレワークの定着を実現させるポイントと注意点』の記事もご覧ください。
帰属意識の向上にはコミュニケーションの活性化が重要!
帰属意識を高めるには、社員同士のコミュニケーションが重要であると考えられます。コミュニケーションの活性化のために重要な役割を果たすのがオフィスです。普段、顔を合わせる機会のあまりない社員同士がオフィスに集まることで、自然とコミュニケーションが生まれやすくなります。オフィスでは社員同士のコミュニケーションを促す工夫も必要です。社員が気軽にコミュニケーションを取れるように、ミーティングスペースや多目的スペースなどの設置も検討しましょう。