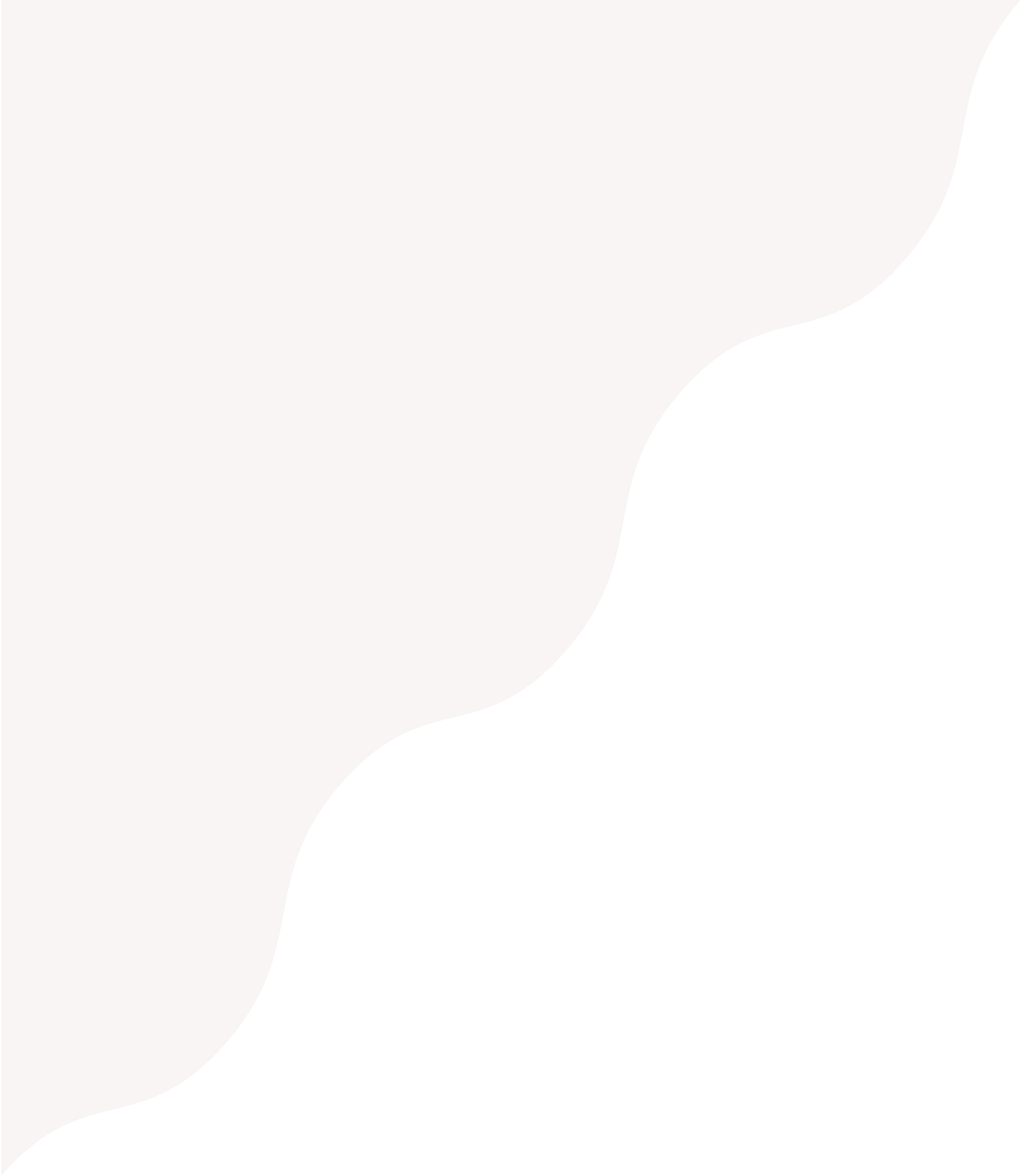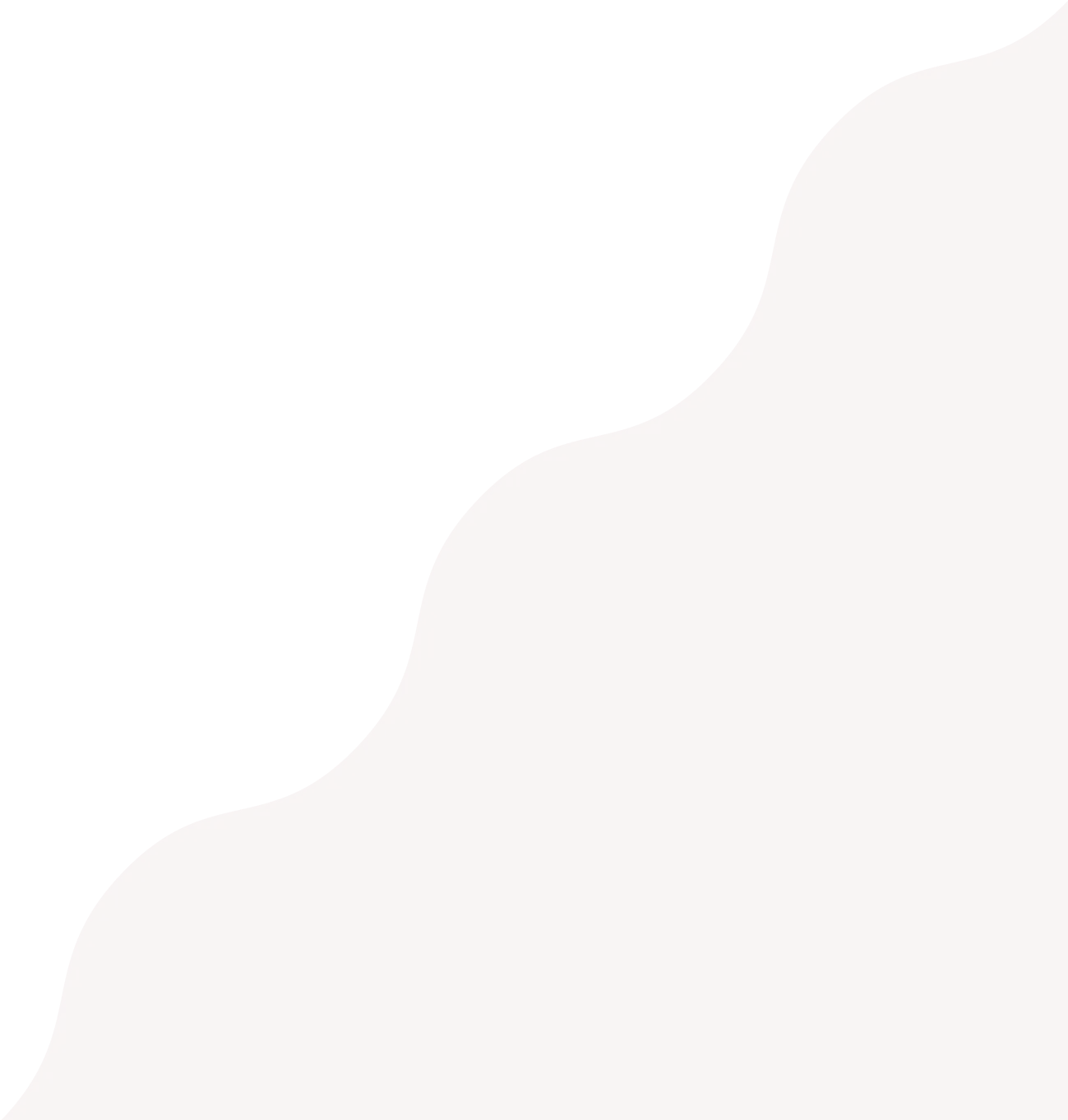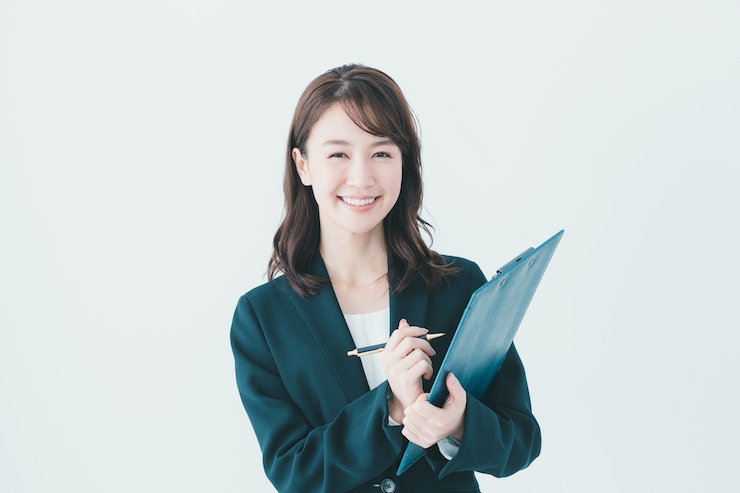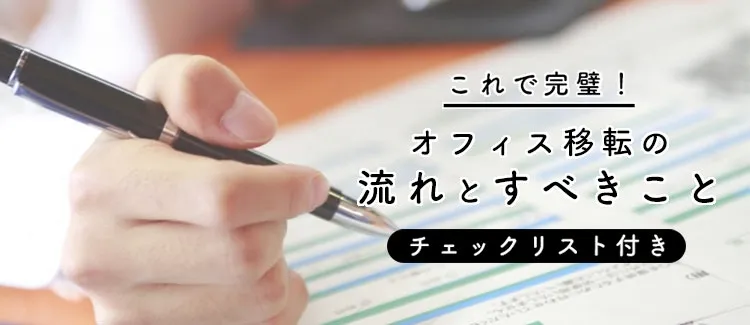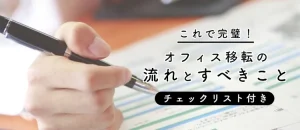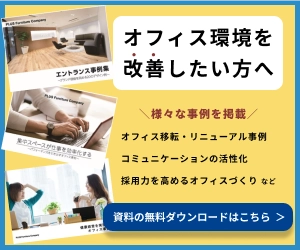緊急事態宣言の解除後、業種によってはオフィスに出社しないと業務がスムーズに進まないとして、テレワークを全面的に廃止する企業も登場しています。しかし一律にテレワークを廃止すれば、従業員からの反発があるのではと二の足を踏んでいる企業も多いのではないでしょうか。そこで今回はテレワークの存続について結論を決めかねている企業に向けて、テレワークを廃止する前に知っておくべきことや廃止を検討する際のポイントをお伝えします。
新型コロナウイルス感染拡大前に戻りつつあるテレワーク導入率
東京都が発表した調査によると、都内企業(従業員30人以上)のテレワーク実施率は、2023年3月時点で43.4%でした。これは前回の2月と同率で、実施率は一定の水準を維持しています。
一方で、実際にテレワークを行った社員の割合は36.0% と、前月の35.2%から0.8ポイント増加しました。
またテレワークを週3日以上行った社員の割合は45.6%と、前回の40.1%から5.5ポイントの上昇を記録しています。これらの結果から、テレワークの導入自体は横ばいながら、頻度や活用の進展が見られることがわかります。
ただしテレワークの活用が続く一方で、国土交通省が発表した令和5年度の都市鉄道の平均混雑率は136%と、前年度比で13ポイント増加しています。
通勤需要がコロナ前の状況に徐々に戻りつつあることを示しており、混雑率が上昇していることは、オフィス勤務の割合が増加している背景を反映しています。
テレワーク廃止する企業が増加している理由
テレワークを廃止する企業が増加している背景には、コロナ禍を経た社会的状況の変化や業務効率の課題が挙げられます。
新型コロナウイルスの緊急事態宣言が解除され、感染防止策としての在宅勤務の必要性が薄れたことで、多くの企業が従来のオフィス勤務へ回帰する動きを見せています。
またテレワークは一部の業界や職種で高い効果を発揮する一方、企業によっては生産性や業務効率が低下する問題が顕著になりました。
具体的には社員間のコミュニケーション不足やチームの一体感の喪失が挙げられ、意思決定が遅れることで業務全体の進行が停滞するケースが見られます。
とくに急遽テレワークを導入した企業では、在宅勤務を支えるIT環境や運用ルールが整備されておらず、成果がともなわないまま運用が継続されたことが原因といわれています。
さらに従業員がオフィス勤務で得られるリアルタイムな情報共有や、対面での連携のメリットを重視する声が企業内で強まったことも廃止の一因です。
テレワークを廃止・縮小することのメリットとデメリット
テレワーク廃止の動きが少しずつ見えてきているなか、まだ方向性を決めかねている企業も多いのではないでしょうか。そこで、廃止の結論を出す前に知っておくべきテレワークを廃止した際のメリットとデメリットを説明します。
テレワークを廃止・縮小するメリット
従業員間・取引先とのコミュニケーションが取りやすくなる
テレワークを廃止・縮小してオフィスワークに戻せば、従業員はもちろん取引先への営業活動も以前のように行えるため、対面でのコミュニケーションが基本となります。その結果、コミュニケーション不足は解消に向かうでしょう。
労務管理がしやすくなる
テレワークでは難しかった在籍や労務管理がしやすくなります。今、誰がどこにいて何をしているのかがわかりやすくなるため、労務全体の管理にかかる手間は大幅に軽減されるでしょう。
セキュリティ管理がしやすくなる
多くの従業員がオフィス内でパソコンやスマートフォンを扱うようになるため、自宅やレンタルオフィスなどに比べセキュリティ管理がしやすくなります。
テレワークを廃止・縮小するデメリット
柔軟な働き方を求める従業員が離職するリスクが生まれる
テレワークを導入する企業が増加したことにより、育児や介護などによりオフィスへの出社が難しい従業員でも従来のように働くことが当たり前となりました。しかし、また以前のようなオフィスワークのみになれば、柔軟な働き方が難しくなり、さまざまな事情を抱えた従業員の離職リスクが高まるうえ、求職者の減少リスクも発生する可能性があります。
従業員のワークライフバランスが崩れてしまう可能性がある
テレワークの導入により、通勤時間がなくなり従業員のワークライフバランスは大幅に向上しました。しかしテレワークが廃止・縮小されればまたワークライフバランスが崩れてしまうリスクが生まれます。
BCP対策が弱くなる
台風や地震といった自然災害以外にも電車の遅延や停止などの際、オフィスワークのみだと業務が滞ってしまう場合があります。テレワークの廃止・縮小はBCP対策が弱くなるリスクがあるといえるでしょう。
テレワークとオフィスのあり方については、『テレワークは継続すべき?改めて考えるテレワーク時のオフィスのあり方』の記事もご覧ください。
テレワークを廃止・縮小する際のポイント
前項で挙げたようにテレワーク廃止・縮小にはメリット、デメリットの両面があり、出社と在宅どちらか一方だけを選択するのは簡単ではありません。そこで、テレワークを廃止・縮小するにしても以前とまったく同じ業務形態にするのではなく、柔軟性は残したままオフィスワークに切り替えていくことが重要です。具体的には次のような方法が考えられます。
就業時間に柔軟性を持たせる
オフィスワークに戻す場合でも、さまざまな事情を抱えた従業員でも就業できるよう、時短勤務やフレックスタイムなど就業時間に柔軟性を持たせるようにします。
必要に応じてテレワークを認める
子育てや介護など特定の理由がある従業員にはテレワークを継続できるようにします。
ハイブリッドワークの導入
テレワークとオフィスワークの両方を適切に活用できる「ハイブリッドワーク」を導入します。この際、対象を決めてしまうと対象外の従業員から不満が出る可能性もあるため、注意が必要です。
ハイブリッドワークについては、『ハイブリッドワークとは?テレワークの定着を実現させるポイントと注意点』の記事で解説しています。あわせてご覧ください。
テレワークの今後の動向について
テレワークを縮小する企業が増加している一方で、その全体的な需要は完全になくならず、新しい形で進化する可能性が示唆されています。
新型コロナウイルスの感染拡大を機に普及したテレワークは、働き方改革の一環として社会に定着しつつありますが、コロナ禍が収束する中で以前と同じ働き方には戻らないとの見方も強まっています。
政府も引き続きテレワークの推進を図っており、総務省と厚生労働省はテレワークを導入・運用する企業を支援する取り組みを展開しています。
その一環として、ICT(情報通信技術)を活用した柔軟な働き方を普及させるための相談窓口「テレワーク相談センター」を設置し、労務管理や技術導入に関する専門的なアドバイスを行っています。
そのほかさまざまな事業や支援を通して、中小企業を含む幅広い事業体がテレワーク導入の課題を解決しやすくなり、多様な働き方を選択する機会が増えることが期待されています。
また企業側も、完全なオフィス回帰やテレワークの全面廃止ではなく、在宅勤務とオフィス出勤を組み合わせたハイブリッドワークを検討する動きが広がっています。
今後は、企業ごとの業務特性や社員のニーズに応じたハイブリッドなテレワーク運用が行われると考えられています。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework
ハイブリッドワークを実現しやすいオフィスの在り方とは
ハイブリッドワークに適したオフィスとは、社員の多様な働き方を支えつつ、業務効率とコスト削減のバランスを取ることができる柔軟性を備えた空間です。
ハイブリッドワークが普及する中で、多くの企業が従来の固定席を廃止し、フリーアドレス制を取り入れる動きが進んでいます。
これまでのオフィスは、社員が決まったデスクで仕事をしていました。
一方のフリーアドレス制は特定の席を持たず、必要に応じて空いている席を利用する仕組みです。
営業職など、外出の多い職種向けの形式として採用されることが一般的ですが、ハイブリッドワークの普及にともなってより幅広い業務に適応する形で導入が進んでいます。
フリーアドレス制を採用することにより席数を削減できるため、オフィスの総面積を縮小し、賃料を削減するというメリットがあります。
またオフィスレイアウトを容易に変更できる柔軟性も備えており、社員が集まってコラボレーションしやすい空間や、集中できるゾーンを設けるなど、多様な働き方に応じた設計が可能です。
オフィスに出社する人数が日々変わるハイブリッドワークでは、従来のような固定席は利用効率が低くなるため、フリーアドレスの導入が合理的なのです。
一方で、フリーアドレス制にはデメリットも存在します。
どこでも仕事ができる環境を整えるために、無線LANやモバイル端末の整備が必要になります。
また社員の所在が把握しづらくなると、業務進行に支障をきたすこともあります。
しかしオフィス利用状況を可視化するシステムの導入や、特定のエリアをチーム単位で確保するなどの工夫によって解決可能です。
テレワークの廃止・縮小は柔軟性を残したまま進めていくことが重要
テレワークは、コミュニケーションや労務管理の困難さなどデメリットを生む一方で、うまく活用すれば生産性向上や従業員満足度向上といったメリットをもたらします。緊急事態宣言が解除されたからといって安易に廃止してしまうのではなく、継続の要否について十分に検討を重ねる必要があるでしょう。
重要なポイントは廃止か継続かといった二元論で考えるのではなく、オフィスワークを基本としながらも状況に応じてテレワークのメリットを生かしていくことです。時短勤務やフレックスタイム制の活用、ハイブリッドワークの導入などをオフィスワークにうまく組み合わせれば、双方のメリットを享受することも可能になります。テレワーク廃止を決める前に改めて柔軟性のあるオフィスワークを検討してみてはいかがでしょうか。